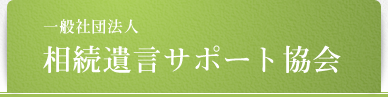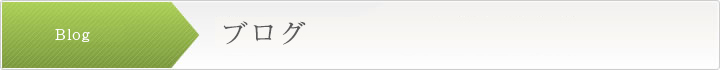弁護士の佐野です。
前回、2022年5月21日号の判例時報2513号に、ちょっと気になる判決が紹介されていましたと書きましたが、実はもう1つありますので、これも取り上げたいと思います。
目次
1. 未成年の子が相続する場合の特別代理人
2. 今回判決の事例
3. 未成年者の特別代理人の義務はどんなもの?
4. 特別代理人に義務がないと、未成年者は守られない?
1. 未成年の子が相続する場合の特別代理人
未成年の子が相続する場合があります。
亡くなった方が遺言を残しておらず、子が未成年である場合
亡くなった方の子が先に死亡していて、未成年の孫が相続する場合
などが考えられます。
未成年の子が遺産分割協議に参加して、他の相続人と交渉するなんて普通は無理ですよね。
まして、相続人は生まれたばかり、なんてこともあります。
この場合、その子の親権者が代わりに交渉することになります(民法818条1項)。
しかし、相続に限らず一般に、親権者も関係者である場合もあり得ます。
そうなると、子の利益を考えると親権者の利益が害される、あるいはその逆、という関係が成立してしまいます。
これを利益相反といいます。
その場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条1項)。
また、子に親権者がいない場合、その子に訴えを起こそうという人は、特別代理人の選任をその裁判所に申し立てることができます(民事訴訟法35条1項)。
家事事件の場合は、裁判官の職権でもできます(家事事件手続法19条1項)。
未成年者が当事者になる場合で、親権者と利益相反になる場合は、特別代理人を選任して未成年者を守ることになっているんですね。
2. 今回の判決の事例
今回の判決は、令和2年12月25日のもので、東京地方裁判所平成30年(ワ)40409号遺産確認等請求事件です。
お父さんが平成6年に交通事故で亡くなってしまった、というかわいそうな事件が発端です。
事故当時、長女は9歳、長男は4歳でした。
妻と幼い子どもが2人、突然パパを失い、残されてしまいました。
何ともかわいそうです。
その後、相続人の妻と長女、長男で、遺産分割協議書が作成されました。
先ほど書きましたように、妻の相続分が増えると長女、長男の相続分が減る、あるいはその逆という利益相反の関係でもあり、特別代理人の選任が必要な事案です。
ところが、遺産分割協議書には、長女の親権者にはおばあちゃんが、長男の親権者にはおじさんが署名してしまいました。
これはまずいです。
非常にまずいです。
これが許されるなら、何でもありになってしまいます。
遺産分割協議書は税理士が作成したので、知らなかったのかもしれません。
たぶん、不動産の登記や預金の払い戻しなど、あちこちで書類が足りないと問題となったのではないでしょうか。
そこで、1ヶ月後、改めて、家庭裁判所におじいちゃんとおじさんを特別代理人に選任するよう申し立てがされました。
これで、手続的には遺産分割協議書が有効となり、処理がなされたと思われます。
その23年後、平成29年になって、長女からこの遺産分割協議の有効性を争う民事調停が起こされ、調停は不成立となり、結局裁判となりました。
これは辛いですね。。。
32歳の長女が、23年前に事故死した父親の相続を争って、60歳の母を相手取ったわけです。
どんな結論になっても、母親との関係でも弟との関係でも大きなしこりが残りそうです。
普通なら事件にはならないと思います。
背景にはいろんな感情が渦巻いてそうですね。
まあ、感情的にはともかく、主な争点は、特別代理人は未成年者の利益のために選任されるわけですが、その特別代理人に、未成年者に大きな不利益をもたらしてはならないという義務があるか、というものです。
ここで問題とされた不利益というのは、金銭面でのものでした。
3. 未成年者の特別代理人の義務はどんなもの?
この判決では、次のように判示しました。
親権者とその親権に服する未成年の子を当事者とする遺産分割協議において、どのような分割方法が子の利益に資するかは、相続財産の内容、その時点における子の年齢や生活状況、今後見込まれる親権者による子の養育監護の状況など個別具体的な種々の事情により異なる。
子にその法定相続分相当以上の相続財産を取得させることが、常に子の利益に資するということはできない。
したがって、上記遺産分割協議において、未成年の子の特別代理人に、常に当該子にその法定相続分相当以上の相続財産を取得させるよう協議する義務はない。
なお、これについては遺留分を侵害する結果となったとしても同様と判示されています。
いろんな事情があるんだから、お金を多く取ればそれが、子の本当の利益になるというわけではないでしょ、ということです。
特別代理人の義務としてとらえると、積極的に何か義務があるという判断はされていません。
少なくとも、特別代理人にお金を多く取る義務があるということはいえないでしょ、という限りで判断されました。
ただ、いろんな事情があるんだからというくだりからして、これは結局、特別代理人の大きな裁量、ほぼフリーハンドを認めたということになろうかと思います。
4. 特別代理人に義務がないと、未成年者は守られない?
特別代理人に、未成年者の財産は一定確保しなさいよという義務がない、ほぼフリーハンド、ということになると、未成年者は守られないのでは?という疑問も生じます。
賛否両論かもしれませんが、子どもの状況は様々ですし、将来のことまで考えると、画一的な線引きは難しいと思いますので、やむを得ないかなと思います。
そもそも、親権者が勝手に決めました、というのではなく、第三者が関与しているので、それだけでも未成年者の保護になるかと思います。
親権者と第三者が結託したらどうするの?ということも考えられますが、それは義務の有無にかかわらず避けようのない危険です。
ちゃんと子どもの生活や将来を考えてくれる特別代理人を選任するしかありません。
今回のケースでは、9歳と6歳の子に大きな財産を残しても、そのお母さんに十分な財産が行かず、子どもにはお金があるのにその運用ができずに生活できない、世帯として回らなくなる、なんてことも考えられます。
また、子どもに財産を渡して、親がそれを使うと、それこそ問題になりかねません。
色々事情を考えられる立場の親族が介入してきてもおかしくない事案かなあと思います。
また、判決の記載によると、被告となったお母さんは、事業を展開する実家を継ぐ決意を固めた夫について、結婚を機に東京から北海道に引っ越してきたそうです。
その矢先、夫を交通事故で失いました。
お母さんは、会社の経営に関わっていたわけでもありません。
夫の財産状況も把握しておらず、会長だったおばあちゃんの指示で税理士が遺産分割協議書を作成し、言われるがまま署名したのでした。
事故後、当時幼少であった子2人と住むために北海道にマンションを購入しました。
また、生活費を確保しようと、不動産賃貸業を営むことを決意して、東京に土地を購入し、8000万円を借り入れて、建物を建てて賃貸に出しました。
長女には、東京都内の私立の中学校、高等学校に通学させてあげ、音楽大学の学費の一部についても負担し、そのために借り入れた奨学金の一部も自ら返済しました。
相当気苦労があったと思いますし、頑張ったのかなとも思います。
ところが、なんと、遺産分割協議で取得した相続財産や、夫の事故の損害賠償金を、自分のためにのみ費消していたと訴えられたわけです。
実際のところは分かりませんが、ほんとに切ない(と思われる)事件でした。
この事件は控訴されているようで、これを書いている時点でどうなっているか分かりません。
いい解決がされているといいのですが。
2022年8月15日