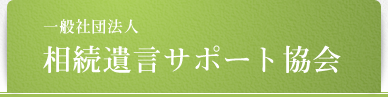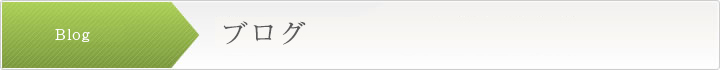弁護士の佐野です。
引き続き、遺留分について書いていきます。
今回は、遺留分を計算するに当たって、どの範囲の財産を基準にすることになるか、です。
4.遺留分を算定するための財産の価額
では、何を基準に遺留分を計算するのでしょうか。
これは、民法1043条1項に計算式が書いてあります。
遺留分を算定するための財産の価額
- =被相続人が相続開始の時において有した財産の価額
- +贈与した財産の価額を加えた額
- -債務の全額を控除した額
となっています。
なお、条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めることとされています(民法1043条2項)。
4.1.相続開始の時において有した財産の価額
これについては分かりやすいですね。
亡くなった方が持っていた財産の、亡くなった時点の価値が基準となります。
なお、これは遺留分の計算の場面ですが、もし遺産分割協議の場面だったとしたら、遺産分割協議成立時点の価値で考えます。
遺留分の計算の前提となる価値を考えるときと、実際に遺産を分けて公平を図るときとで違うわけですね。
遺留分の計算の前提となる価値を、実際に紛争が解決する時点で計算するとしてしまうと、争っている間に金額が変動したら、いつまでも計算できなくなってしまいます。
逆に、遺産分割協議の成立の時に、現在の価値が大きく変動していれば、不公平だと文句が出て協議成立とはならないでしょう。
4.2.贈与した財産の価額を加えた額
相続開始の時において有した財産の価額が分かると、次は贈与を加算します。
でないと、亡くなる直前に大きな財産を贈与してしまえば、遺留分の制度は意味がなくなってしまいますからね。
そのため、贈与した分を加算して計算することになっています。
これを「持ち戻し」といいます。
これについては、民法1044条と1045条に規定されています。
これまた細かいので、分けて見てみましょう。
なお、民法1046条1項には、「特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。」とされていて、贈与に含まれるものが他にもあるよということになっています。
これは、特定の財産を相続させますよという遺言と、この人の相続する割合はこれだけ確保してねという遺言の場合が含まれるということです。
4.2.1.贈与の相手によって変わる
贈与は、相続人にする場合と第三者にする場合とがあります。
おじいちゃんが、生前に相続人ではない孫に贈与したと思ったら、おじいちゃんが亡くなるまでにおじいちゃんの子で孫の親が先に亡くなってしまって、孫が相続人になった、ということもありそうです。
こういう場合、扱いが変わってしまいます。
民法1044条では、
- 第三者:相続開始前の1年間の贈与(1項)
- 相続人:相続開始前の10年間の贈与(3項)
が対象になります。
第三者がもらったと思って安心していたのに、何年も前のことで巻き込まれてしまうということになったら大変です。
なので、1年間と区切られています。
他方、相続人は、10年もの間対象とされてしまいます。
しかし、相続人の場合は「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る)」と限定されています。
これは、特別受益(民法903条1項)のうち遺贈を除外したものですが、遺贈はそもそも遺言で贈与するものなので、すでに計算に含まれていて、ここで問題となる生前の贈与とは関係がありません。
つまり、特別受益に合わせた、ということになります。
ややこしいですね。
以前は、いつまでもさかのぼって問題にされましたが、あまりに古いのはもういいでしょ、10年でええんとちゃいますか、ということになりました。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、無制限となります。
贈与した被相続人ともらった方の両方が、遺留分を侵害するよと知っていたら、1年も10年も関係ないということになります。
これは、相続人かどうかに関係ありません。遺留分権利者を害すると分かってたのなら保護する必要はないよね、ということです。
ただし、立証の問題は残りますので、不動産とか履歴が分かりやすいものに限られることになるでしょうね。
贈与の価格は、亡くなった時点の価値で決められることになります(民法1044条2項、904条)。
贈与した時点では5000万円の土地だったが、亡くなった時点では1億円に跳ね上がっていた、揉めに揉めて解決した時点では3000万円に下がっていたという場合、1億円で計算されるということになります。
贈与は特定の物で行われるものですが、相続分の贈与も同じように扱われます。
例えば、お父さんが亡くなって、お母さんと子2人が相続したとします。
お母さんは自身の相続分2分の1を長女に贈与しました。結果、長女が4分の3、長男が4分の1を相続したとします。これ自体は何の問題もありません。
その後すぐお母さんが亡くなったとすると、お母さんがお父さんの相続の時に贈与した相続分2分の1が、お母さんの相続の時の遺留分侵害ということになる可能性があります。
子どもの1人をひいきするというのはよくある話です。
後ほど書きますが、遺留分侵害額請求権の期間の制限内でそういうことがあったら、要注意です。
弁護士も見過ごしがちだと思いますので、気をつけましょう。
4.2.2.贈与が負担付きの場合
単純に、おじいちゃんがくれたラッキー!で済む贈与ならいいのですが、あげる代わりにこれしろよ、という負担付きの贈与もあります。
1億円の土地をあげるから、その代わり5000万円の借金を返済してね、ということもあるかもしれません。
1億円の自宅をあげるから、おばあちゃんが死ぬまで、おばあちゃんをしっかり面倒見てあげてね、ということもあるかもしれません。
1億円の家業の店をあげるから、しっかり店を守っていってね、ということもあるかもしれません。
こういう場合には、その負担分を差し引いた部分を加えることになってます(民法1045条1項)。
また、贈与ではないけど、バランスの悪い売買など、露骨に贈与に近いものについては、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限って、同じように扱われます(民法1045条2項)。
これは当然ですね。
しかし、この計算や評価は非常にやっかいです。
土地をもらったけど借金も背負うということになったら、その利息は入るのか?
1億円の土地をもらって5000万円の借金も背負うことになって、すぐに5000万円返済できればいいですが、30年で返済するとなると、かなりの利息を支払うことになります。
おばあちゃんが死ぬまで面倒を見るのはどう計算すればいいのか。
店を守るにも、順調ならいいですが、コロナ禍で風前の灯火の飲食店ならどうなの?
いや~、こういうのは頭を抱えます。
こういうのを明快に解説しているサイトや本があれば教えて欲しいです。
おそらく、お茶を濁しているのがほとんどではないでしょうか。
こういうのは、争ってみないと分かりません。私はそう思います。
4.3.債務の全額を控除した額
相続開始の時において有した財産の価額が分かって、贈与した財産の価額を加えた額が判明したら、最後に被相続人の借金を差し引きます。
これも分かりやすいですね。
2022年4月25日