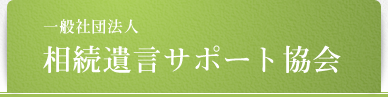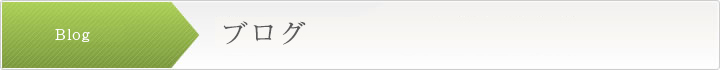弁護士の佐野です。
今回は、遺言執行者について書いてみたいと思います。
私はあちこちで、遺言には遺言執行者を指定しておきなさいよと書いてきました。
相続法改正により2023年4月1日から、遺言執行者の取り扱いが変わるので、先んじて(これを書いている時点では)触れておきたいと思います。
法改正との絡みもあるので、概ね条文の順番で書いていきたいと思います。
目次
1. そもそも遺言執行者って何?
2. 遺言執行者の地位
3. 遺言執行者の任務の開始
4. 遺言執行者は何ができるの?
5. 一部の財産についてだけの遺言執行
5.1. 特定の財産が物の時
5.2. 特定の財産が預貯金の時
6. 遺言執行者の復任権
7. 遺言執行の妨害の禁止 1
8. 遺言執行の妨害の禁止 2
9. まとめ
1. そもそも遺言執行者って何?
遺言執行者とは、文字通り遺言の内容を執行する人、ということになります。
遺言をするのは簡単ですが、実際に遺言の内容を実現する際には、預金を引き出したり、遺産を売ったり、登記をしたりなど、いろんな手続が必要になります。
遺言は、作成しただけで、これで安心とほっとする方が多いと思いますが、遺言はきちんと執行されてやっとその役目を果たします。
遺言が複雑であればあるほど、あるいは相続人が揉めそうだったりするなど、懸念はつきまといます。実際には、遺言を作成した人が思ったほどには上手くいかないので、残された方は大変な思いをすることがあります。
そのため、信頼できる人に、この遺言を実現してね、とお願いして、きちんと遺言執行者として指定しておくのがいいのです。
これは権利として定められています(民法1006条1項)。
遺言作成を依頼した行政書士にそのままお願いする、任意後見をお願いできるほど信頼できる司法書士に一緒にお願いする、財産も多く相続人も仲が悪いので信頼できる弁護士に依頼する、といったこともありますし、頼りになる長女、慕ってきた兄、できのいい甥っ子になってもらうということもあると思います。
2. 遺言執行者の地位
遺言執行者の地位といっても、別に大したお話ではありません。
改正前は、遺言執行者は、相続人の代理人とみなすとされていました(改正前民法1015条)。
遺言執行者は、遺言を実現する、つまり遺言を書いた被相続人の意思を実現する人です。
いわば、相続人ではなく被相続人の代理人です。
被相続人とは、相続される亡くなった方のことです。
例えば、お父さんが亡くなって、妻と子が相続する場合の、お父さんのことを被相続人といいます。
用語が分かりづらいかもしれませんが、ここは頑張って慣れてくださいね。
で、この場合なら、遺言執行者はお父さんの代理人になるのが筋です。
ところが、理論上、亡くなっている人の代理人というのはあり得ないんです。
そこで、相続人、上の例では妻と子の代理人とされていました。
ところが、代理人は本人、つまり相続人のために動かないといけないわけです。
遺言に、遺産を他の人にあげるとか、一部の相続人に多くあげるとか書いてあると、遺言執行者は不利益を被る相続人のためにも動かなければなりません。
これっておかしいでしょ、という問題がありました。
そこで、改正法では、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる、として、単なる代理人ではないですよ、ということにしました(改正民法1015条)。
素人の方がこの条文を読んでも、よく分からないかと思います。
これにどういう意味があるのかは、結論は変わらないのと、難しいのでここでは触れませんね。
3. 遺言執行者の任務の開始
遺言執行者は、就任を承諾したときは、直ちに任務を開始しなければなりません(民法1007条1項)。
「就任を承諾」というのは、必ずしも事前に遺言執行者が決まっているわけではないからです。
遺言で、遺言執行者は誰かいい人に決めてねと第三者にお願いすることもできますし(民法1006条1項)、家庭裁判所が決めることもあります(民法1010条)。
また、そもそも勝手に指名されているだけのこともあり得ます。
そのため、自動的に任務が開始されるだけではなく、事前に、やりますよ~と承諾するということがあり得るのです。
もちろん、遺言者が亡くなってからの話です。
直ちに任務を開始して、まずしなければならないことは、遺言の内容を相続人に通知することです(民法1007条2項)。
これは、改正法で決められました。
遺言の内容を通知するということは、自分が遺言執行者です、ということも通知するということです。
第三者が遺言執行者を指定してねと言われていれば、遅滞なく、その指定をして、誰が遺言執行者になったかを相続人に通知しなければなりません(民法1006条2項)
ところが以前(これを書いている時点では今ですが)は、遺言執行者が指定されていれば、通知しなくても良かったのです。
となると、相続人の知らない間に全部終わってた、なんてことがあり得たわけです。
ドラマのような、大金持ちの隠し子だったことが大金持ちが亡くなってから判明してすごい展開になるようなことよりも、隠し子であることも知らされずにそのまま遺産分割からのけ者にされていた、ということがほとんどだったのではないでしょうか。
法律上、そういうことが解消されたことになります。
2022年2月28日