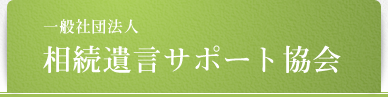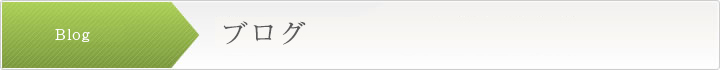税理士の岡本です。
今回は、相続に関する主な手続きと期限について書きたいと思います。
ご家族が亡くなると、しなければならない手続きがたくさん発生します。
まずは、医師から「死亡診断書」をもらい、役所に「死亡届出」と「火葬許可申請書」を出します。
すると役所からは「火葬許可証」が交付されます。それをもらって、葬儀の準備を始めることができます。
ちなみに、死亡届は、7日以内に出さなければなりません。(戸籍法86条)
この「死亡診断書」は、色々なところで必要になるのでコピーをしておきましょう。
役所に行ったときには、後々、亡くなった方の除籍謄本や、その方の生まれてから亡くなるまでの戸籍情報が必要となるので、ついでに改正原戸籍(原戸籍ともいいます)を取っておくようにしましょう。
公的な手続きとしては、年金受給者であれば年金受給の停止手続きや、健康保険・介護保険の資格喪失届出の提出が必要となります。
ここで、区切りとして注意しておく必要があるのが、3ヶ月、4ヶ月、10ヶ月です。
亡くなった日の翌日から3ヶ月とは、3カ月以内に遺産を相続するか、相続を放棄するかを決めなければならない期間です。
ご家族が亡くなって3ヶ月ですので、ふと気付いたら過ぎてしまいかねない短さです。
あまり時間はありません。
生前にどういう債権債務があるかの確認をしておきましょう。
といっても、子どもからはなかなか聞きにくいですが…。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所で手続きが必要です。
なお、家庭裁判所に申し立てれば、この期間は伸ばすことができます。
次に、4ヶ月というのは、亡くなった人がその年に得た所得を計算して確定申告をする期限です。
準確定申告というのですが、申告をして納税があれば納税までしないといけません。
最後に、10ヶ月というのは、相続税の申告が必要なら、相続税の申告・納税の期限です。
この申告までに、相続人全員で遺産分割協議をして遺産を分けないといけません。
もし不動産があれば、名義変更する相続登記が必要となります。
このように、亡くなってから10ヶ月の間に、しなければならないことはたくさんあります。
期限は次々と、あっという間にやってきます。
そのため、生前に、残される家族のために準備をしておくのは大事なことです。
それでも手続きは大変なことなので、専門家に相談することをお勧めします。
2021年11月5日