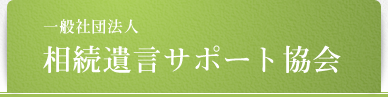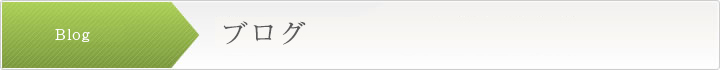弁護士の佐野です。
相続人がどれだけ相続できるかは、次のとおりの順番で決まります。
- 話し合い
- 遺言
- 法定相続分
この順番は、どれだけ揉めるかの順番でもあります。
相続人の間で仲良く話し合いができるのであれば、誰がなんと言おうと、どのような分け方をしてもかまいません。税金さえきちんと納めれば、誰に何を言われる筋合いもありません。
この場合に揉めるのは、相続人である夫または妻の妻または夫がうるさい(もらえるものはもっともらえ)とか、被相続人である亡くなった方の兄弟(相続人からはおじさんおばさん)が口を挟んでくる(家を守れ)とか、そういうことが多いでしょう。
ただ、自由に分けてもいいとなると、借金は?金を貸して財産がない人が借金を引き受けたら、取りっぱぐれることにならない?ということも心配になりそうです。
しかしそこは、貸す側がしっかりしなさいよ、というのが法の建前になっています。
貸す側を守る制度として、抵当権や保証人といったものもあります。
貸すときに、借りた人が亡くなることも想定して対策が取れるんですよね。
それをしていないのは、していない方の脇が甘かった、ということになってしまいます。
ここは注意しましょう
親族間や友人間の貸し借りなどでは、往々にしてこういったことが起きます。
きちんと返してもらうには、生前に、借りた人の周囲の理解を得ておくことが大事でしょう。
相続人が、「この人だけには返さないといけない」と思える信頼関係を築いておくことが大事です。
逆に言うと、安易な貸し借りは回収できない、と思っておくことが大事です。
では、財産が1000万円と借金が100万円ある人が亡くなって、2人の相続人がいるという場合、一方が財産の1000万円を相続し、資産のない他方が借金100万円を相続したら、実質的には回収できないのか、ということになりそうです。
これについては、法定相続分に従って請求することができるということが定められています(民法902条の2)。
上の例では、相続人2人に、それぞれ50万円ずつ請求できるということになるわけです。
お金のない人に借金だけ押しつけた相続をして、踏み倒すと言うことはできない、ということになります。
相続人の間で話がまとまらない場合、もし遺言があれば、それに従うことになります(民法902条。遺留分という制度はあります)。
話がまとまるのであれば、遺言は無視してかまいません。
なので、話がまとまらないときに効果が出てくるのが遺言です。
話がまとまらないとき、お父さんがこう言っているならそれに従おう、そういうまとまり方をしたおかげで、お父さんのおかげで泥沼の争いを避けられた、親族の決定的な亀裂を避けられた、ということも多々あります。
そういう意味では遺言は、相続人の間で話がまとまらないときに、亡くなった被相続人が意思を反映したいときのためのものとか、相続人を争いから守るためのもの、ということもいえますね。
この相続遺言サポート協会で作成のお手伝いをしている遺言は、相続人を争いから守るためのものです。
亡くなった方と相続人との間にどういった歴史があり、どういった方が相続し、亡くなる方の気持ちをどう伝えれば伝わるのか、法的に弱点はないか、つけいる隙を与えていないか、税金対策はできているか、といったところを徹底的に詰めて、作成のお手伝いをします。
どういった遺言を作成すべきかは人によって変わります。全てオーダーメイドです。お金がなくても揉めます。逆にお金持ちは揉めることは少ないです。どなたでも、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
話し合いがつかず、遺言もない場合は法定相続分で遺産分割することになります(901条)。
遺言があっても、その内容で争いがあったり、偽造など遺言そのもので争いがあったりすると、全く違う話になりますので、注意してください。
この場合、話がまとまらず、遺言もないので、結局法律に従うことになります。
法定相続分でいいや、というような結論は、話し合いによる遺産分割が前提になりますが、ここでの話は、話がまとまらないことが前提になりますので、法律の手続きによる法定相続分での遺産分割、ということになります。
結論は単純に法定相続分、ということになりますが、言葉としては一言でも、そこにたどり着くのがこれは結構大変でして、遺産分割調停を経てということになります。
長い調停で10年という話を聞いたことがあります。1年以上かかるのは当たり前です。
その間ずっと争い続けることになるので、仲良しも犬猿の仲になりかねません。争い方が下手だと、金は取れたがご縁は切れた、ということになりかねません。
わざわざけんか腰で争っても仕方ありません。慎重に進めていくのが妥当ですので、これもご相談いただいてご依頼いただくのがいいかと思います。
2021年8月14日